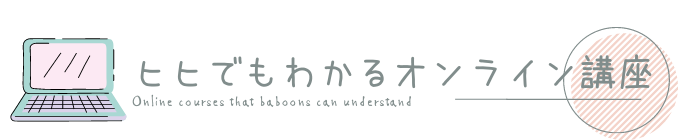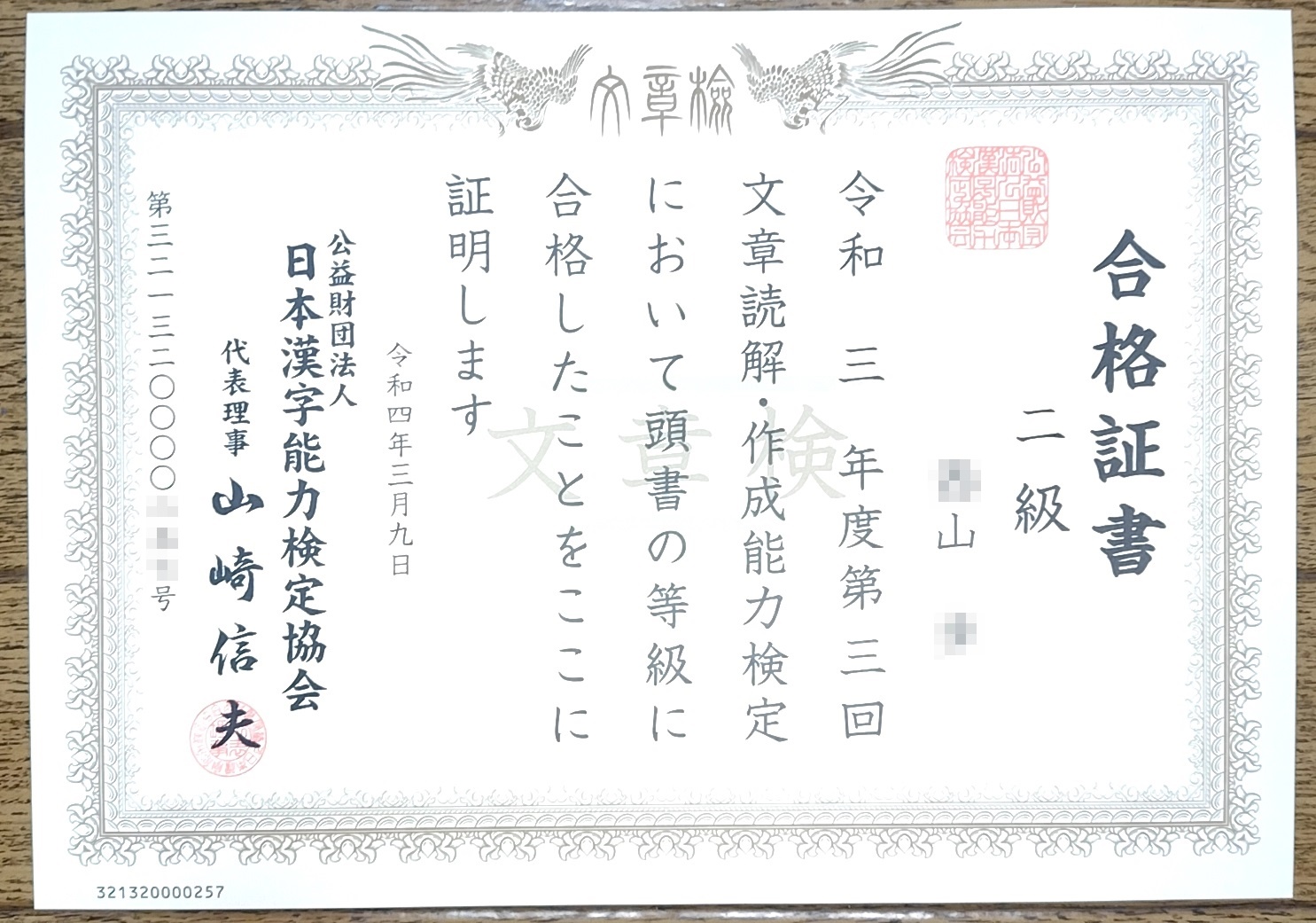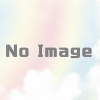【体験記】文章検定(文章読解・作成能力検定)2級に合格した際の勉強時間・勉強方法・教材について
2022年2月13日、文章検定(文章読解・作成能力検定)2級を受験し、無事合格しました。
この記事では、以下の内容を中心にまとめたいと思います。
- 文章検定2級合格までの勉強時間
- 文章検定2級で使った参考書と勉強方法
- 文章検定2級の概要
文章検定2級、合格体験記のまとめ
- まずは過去問から勉強を始めた方がいい(手紙以外の問題は、勉強がほぼ不要な可能性あり)
- 試験対策は、大問1~4ごとに異なる(自分は第3問以外はほとんど対策不要でした)
- 合格だけ考えるなら公式テキストの「語彙・文法」は不要(出題されないので)
- オススメは過去問のみでの学習。心配なら2冊以上購入する
- 文章読解は200点中40点(要約を読解に含めても200点中70点)。メインは文章作成
- 恐らく難関は第3問の「手紙文の作成」
- 論説文の経験次第で中学生でも合格を狙える。高校受験に使うなら中2で挑戦
- 文章と言えばブログと脚本以外ほぼ書かない自分でも、10時間未満の勉強で9割を超える点が取れた
文章検定2級の受験前スペック
簡単に受験前のスペックをまとめると、以下の通りです。
- 高校時代の国語の成績は普通(記録が無いですが、偏差値50前後かと思います)
- 大学は情報系
- 仕事の文章は、定型文・短文中心の報告書が9割以上
- 手紙(お礼、お詫び、依頼など)の作成経験はなし
- 論説文の作成に役立ちそうな経験は「高校の授業」「就活の小論文」「プロジェクトマネージャ試験の論文」「ブログの執筆」
- 4カ月程前から、フィクションの文章を書いてる(試験では役に立ちませんでした……)
一言でまとめると「手紙の作成能力は無し。それ以外は、仕事で全く経験の無い人よりは有利」といったところ。
文章検定2級は200点満点ですが、最後の論説文が配点80点と高め。そして、この論説文は、私が過去に受験したプロジェクトマネージャ試験の論文に比べるとかなり簡単でした。
プロジェクトマネージャ試験の論文では「下書きなしでガンガン文章を書いて、文字数の帳尻を合わせる」というのが普通なので(じゃないと制限時間に間に合わない)この下書きなしで文字数をコントロールする経験もかなり活きたかなと思います(とはいえ、1年半程前の話ですが…)。

文章検定2級、合格までの勉強時間は9時間19分
勉強時間は9時間19分になりました(Studyplusで計測)。
私は日本語検定の1級を視野に勉強していたこともあり、念のためテキストからじっくりやりましたが、これは合格だけ考えれば効率的とは言えない勉強方法です。
また「時候の挨拶」や「手紙の例文」の問題作成に1時間くらい消費しましたが、これもほとんど役に立たず、結局は過去問と解説の読み込み中心の対策が合格への最短ルートでした。
人にもよるかもしれませんが、多少文章を書きなれている社会人なら、過去問を1冊分やって出題形式に慣れ、後は第3問の対策だけ3~5時間くらいやっておけば十分という印象です。
文章検定2級は高卒くらいの文章レベルがあれば、数時間の勉強で合格できる人も多いかと思います。まずは早めに過去問に一度取り組み、自分の実力を確認しておくことをオススメします。
文章検定2級で実際に利用した教材
基礎から学べる! 文章力ステップ 文章検2級対応
自分には不要でした。
確かに、基礎から学べる構成にはなっているのですが、その為に実際の試験には出てこないような内容が入っています。
また、実際の試験に近い内容にしても、やや実際の過去問と出題傾向が違っているように見受けられ、「試験で点数を取る」という目的にはあまり適していない印象です。
中学生や高校1年生など、まだ文章力に不安がある人であれば、基礎からの学習として利用できるかなと思います。
文章検 過去問題集 2級
その名の通り、過去問題集です。合格だけを考えるのであれば、正直この1冊で十分だと思います(心配なら過去問2冊)。
5回分の過去問が収録されており、実際の試験と同様の解答用紙もついています(ただ、記述式はPCでの練習を推奨します)。
回答については、例文も掲載されているため(要約問題を除く)、公式の見解で「どの程度のレベルの記述が求められているか?」がわかります。
ちなみに、私が購入したのは中古で安かった「Vol.1」の方。内容は2015~16年度でしたが、2022年2月13日の試験でも十分通用しました。
文章検定2級の勉強方法
ここでは自分の行った勉強を元に、高校生以上のレベルの人向けに勉強方法を解説します(高卒から10年くらい国語の勉強をしてない社会人でもOKです。高校受験に向け勉強中の中学生も、この勉強でいける人が多いかと思います)。
まず、文章検定2級の出題内容は以下の通りです。
- 第1問 レポートの構成(配点30点):レポートの見出しや、文章の空欄箇所を、選択肢から選ぶ問題(全て選択式)
- 第2問 要約文の問題(配点40点):本文と要約文を見比べて、選択肢から選ぶ問題(10点)、要約文の途中の文章を作成する問題(配点30点)
- 第3問 手紙文の作成(配点50点):内容は「お礼」「お詫び」「案内」「依頼」などの
- 第4問 論説文の作成(配点80点):指定された4段落の構成で論説文を作成する。テーマは変わるが指定の構成は毎回同じ
この第1問~第4問について、それぞれ個別に対策します。
ただ、過去問を一、二度やってみると、出題者の意図がわかるようになる為、社会人レベルであれば「第3問 手紙文の作成」以外は対策不要になる可能性が高いかと思います。
ちなみに、大半が記述問題で、普通に手で書くとかなり時間がとられるし、疲れます。
ですので「本番同様で時間を測定したい」という目的が無い限り、パソコンで文章を作成することをオススメします。私は毎回パソコンで文章を書いていたので、過去問1回あたり、採点も含めて40~60分程度でした。
第1問 レポートの構成
出題内容は、主に以下の2種類です。
- レポートの見出しを選択肢から選ぶ(10点程度)
- 既にある見出しに対して、適切な小文を選択する(20点程度)
正直、大学受験で偏差値50の現代文の方がよほど難しいです。大学受験から離れて14年程度経過しているおっさんでもほぼミスなしのレベルです。
それでも、出題者の意図の癖はあります。なので、過去問題集5年分をやってみて、間違えた場所があればマークを付け、そこだけ直前で理由を見直しておくといいでしょう。
ちなみに勉強時間については、5年分解いても1時間もかからないレベルです。自信があればそもそも勉強を飛ばしてもいいですが(それでも楽勝だと思うし、配点が低い)、念のため過去問に目を通すくらいはやっておきましょう。
第2問 要約文の問題
出題内容は、主に以下の2種類です。
- 本文と要約文を見比べて、選択肢から選ぶ問題(10点)
- 要約文の途中の文章を作成する問題(配点30点)
選択式の問題は「本文と要約文の空欄箇所には同じ言葉が入る。その言葉を選択しなさい」とか「本文を読んで、要約文の省略可能な部分を選択しなさい」といった内容です。対策は「第1問」同様に「とりあえず解いて、間違えた場所だけ試験直前に理由を見直す」で十分でしょう(配点も少なく難易度も高くないので)。
一方、要約文の問題は「残す必要がある言葉をギリギリまで絞り込む」ことが求められる問題です。削り落としても成り立つ言葉を残してしまうと、けっこうな確率で「文字数が足りない!」という状況になります。
といっても、これも「ギリギリまで絞り込む問題」と知っていれば特別な対策は不要で「とりあえず過去問演習を5年分やる」でOKです。演習の際の注意点は「本文の不要な部分はどこか?」の根拠を考えながら取り組む事。文字数制限がギリギリなので「不要な部分」を削った本文をつなげば、必然的に合格の文章になります。
第3問 手紙文の作成
恐らく、最も対策が必要なのがこの「手紙文の作成」です。内容は「お礼」「お詫び」「案内」「依頼」などの手紙のどれか一つを指示通り書くことになります(複合の様な手紙もある)。
概ね、覚えるべきことは以下の通りです(全てが毎回問われるわけではありません)。
この中で「頭語と結語」については毎回「拝啓・敬具」のパターンなので、勉強不要かなと思います(別のパターンが出たら、捨てる問題だと思います)。
「記書きの書き方」については正確には知らない人も多いかもしれませんが、一度覚えれば複雑ではありません。
暗記が大変なのは「時候の挨拶」です。季節感でけっこう暗記はしやすいのですが、量は結構膨大です。ただ、同じ時期で複数の時候の挨拶があり、また1つの言葉で長期間使えるものもあるため、1年を網羅するだけなら、覚えるべき時候の挨拶はある程度減らすことができます。
私の場合、以下の事項の挨拶を暗記しました(「似た言葉」と「長期的に使える言葉」を採用することで、暗記しやすくしました)。
- 1月上旬:新春の候
- 1月中旬:寒中の候
- 1月下旬:厳寒の候
- 2月上旬:晩冬の候
- 2月中旬:梅花の候
- 2月下旬:向春の候
- 3月上旬:早春の候
- 3月中旬:春色の候
- 3月下旬:春分の候
- 4月上~中旬:陽春の候
- 4月下旬:晩春の候
- 5月上~中旬:新緑の候
- 5月下~6月上旬:青葉の候
- 6月中~下旬:向暑の候
- 7月:盛夏の候
- 8月上~中旬:晩夏の候
- 8月下旬:残暑の候
- 9月上旬:初秋の候
- 9月中旬:爽秋の候
- 9月下旬~10月上旬:秋色の候
- 10月中~11月上旬:紅葉の候
- 11月中~下旬:向寒の候
- 12月上~中旬:師走の候
- 12月下旬:歳末の候
ただ、実をいうと全部暗記が必須ではありません。「時候の挨拶」も過去問を見ると「夏休みのお礼」といった形で出題されることがあり、公式の回答では7~9月の時候の挨拶ならOKでした。なので「盛夏の候」とか「晩夏の候」とか「残暑の候」とか1つでもわかれば正解となります。
「手紙らしい言葉遣いをかけること」について
最後に「手紙らしい言葉遣いを書けること」について。これが最も曖昧で対策しにくいです。
日頃書きなれている人なら問題ないと思いますが、私はそういった仕事にはついていないため、過去問の例文から少しずつ暗記するようにしました。
また解答例のパターンの傾向から、以下の様な点には注意しました。
- 「ますますご清栄(ご清祥などでも可)のこととお喜び申し上げます」は多用されるので、「個人向け」「企業向け」などで書き換えできるようにする
- 「お礼」なら、所々の文末に「(本当に)ありがとうございました」などをつける
- 「お詫び」なら、所々の文末に「(本当に)申し訳ございません」などをつける
- 「依頼」なら所々に「○○くださいますようお願いいたします」「○○いただけましたら幸いです」などをつける
- 基本的には余計なことは書かず、問題文で指示されたことを簡潔に書く(ボロをださない)
- 自信の無い漢字や表現は、簡単なもので書き換える
- 解答例で書けなかった表現・漢字は暗記する
第4問 論説文
論説文は配点が最も高く、文章量もかなり多めです。
ただ、毎回出題パターンが決まっていて「一つのテーマについての是非を、全四段落の構成で論述する」という形式です。
その段落の構成は、以下のようになります。
- 第1段落:テーマについて、出来事・体験・知識を述べる
- 第2段落:テーマについて、自分が是か非のどちらの立場かを述べる
- 第3段落:意見の根拠を論理的に説明する
- 第4段落:自分の反対の立場の意見を取り上げる。その上で、その意見が正しくない事を説明する
このように、文章の流れが決まっている上、「是か非かそのものに正解はないテーマ」に対する論述なので、論理的に完全な破綻をしない限り、知識はほとんど必要ありません。更に言ってしまうと「論理に決定的な欠点が見られる」という採点結果であっても、その他にミスが無ければ80点中70点は取れてしまいます。
要するに、フォーマットが整っていて、指定された条件で程々に無難な意見が書ければ、信憑性が全くない「居酒屋の酔っ払いのような意見」であっても合格点には達します。
全体の文字数について
あくまでも傾向ですが「第2段落」については、「是か非か」を述べるだけの部分なのでかなり文字数は少なめになります。
その為、「第1段落」の文字数が少ない状態で「第3段落」「第4段落」の話が膨らまない場合、大幅な書き直しが必要になる可能性があります。
そんなこともあって、私の場合は「第1段落」でわざと長々と自分の経験を語るようにしていました。これにより、第2段落までで全体の半分くらいの文字を稼ぎます。
このように「ダラダラと経験を語ったら減点されるのでは……」とも思いましたが、過去問の解答例では第三、四段落の伏線にならない「テーマに関する自分の行動」や「それに対する周囲の反応」が長々と書かれていました。ですので、「テーマと関連性がある限り、第一段落を長々と書いて問題ない」と判断し、この戦略をとりました。
実際の文章検定2級当日
試験は2月13日の15:00から。國學院大學渋谷キャンパスでした。

渋谷の駅から徒歩15分近い場所ということ、また15分前を目安に受験教室までお越しくださいという事だったので、早めに向かいました。
当日はあいにくの雨。しかも寒い。そしてコロナ影響で直前まで入れず寒い中若干濡れながら20分ほど建物の前で待機。カイロなどを持ってきていなかったため、若干手が冷たいまま試験開始となりました。

ちなみに、ものすごく油断していたので腕時計も無し。教室に時計もないので、試験管の知らせる45分経過と80分経過(終了10分前)のお知らせ以外、時間不明でした。
私は下書きなしで全問解答したので、45分と少し(たぶん55~60分くらい)で見直し含めて試験終了。下書きを使う場合、残りの30分で行う必要があるかなと思います。

文章検定2級の試験結果
文章検定2級の試験の結果は、以下のようになりました。
- 第1問 レポートの構成:30点(30点中)
- 第2問 問1要約文の完成:10点(10点中)
- 第2問 問2要約文の完成:26点(30点中)
- 第3問 手紙文の作成:45点(50点中)
- 第4問 論説文の作成:70点(80点中)
- 合計181点(200点満点。合格点140点)
合計181点で合格。9割を超えることができました。
また、結果の詳細については以下の様に詳細の公表がありました。
「第2問 問2要約文の完成」「第3問 問2要約文の作成」については、表記や文法などのミスがあった可能性が高そうです。
また「第4問 論説文の作成」については、「条件に適合していれば、内容はいい加減でかまわない」となめてかかった為か、論理性で減点になったようです。とはいえ、やはり「内容がいい加減な文章」でも80点中70点取れていたので、戦略としては想定通りと言えます。
点数分布を見ると、「合格者平均」と「大学生・一般平均」では、「第4問 論説文の作成」に大きな差があるようです。ただ、これは「不合格者の多くが、第4問(最後の問題)が完成せずに落ちるパターンが多いから」という可能性もあります。「第4問 論説文の作成」が配点的に重要であることは確かですが、難易度が高いとまでは言えないかなと思います。
そもそも「文章検定(文章読解・作成能力検定)」とは?
文章検定は「公益財団法人 日本漢字能力検定協会」によって運営されている検定です。私が受験した際も、同じ建物で漢字検定も行われていました。
元は「日本語文章能力検定」という名称でしたが、2009年8月の試験を最後に休止。2013年より現在の「文章検定(文章読解・作成能力検定)」の名前で再開されました。
文章検定の試験日・受験費用・合格率
詳細は変更の可能性がありますので、受験の際は公式サイトの確認をお願いします。
個人受験は年に1回、2月の概ね第二日曜に行われています(団体受験は年に6回。ただし2級は1回のみ)。
受験料は以下の通りです。
| 受験級 | 受験料 |
| 2級 | 4,000円 |
| 準2級 | 3,000円 |
| 3級 | 3,000円 |
| 4級 | 3,000円 |
合格率は非公開となっていますが、どの級もおよそ70%程度とのことです。
ちなみに、1級は現状では存在せず、2級が最高となっています。
文章検定の受験資格
全ての級で受験資格なしで受験できます。
文章検定の試験時間・合格基準
試験時間は以下の通りです(合格基準は調整されることがあります)。
| 受験級 | 検定時間 | 公開会場(日曜日)の実施時間 |
| 2級 | 90分 | 15:00~16:30 |
| 準2級 | 60分 | 15:00~16:00 |
| 3級 | 60分 | 15:00~16:00 |
| 4級 | 60分 | 15:00~16:00 |
また、合格基準は各級で200点満点で70%になっています。
文章検定の難易度
各級の難易度は以下の通りです。
| 受験級 | 難易度 |
| 2級 | 高等教育で高度な教養を主体的に身につけるために、あるいは、社会人として求められる文章作成を行うために必要な総合的な文章読解力及び文章作成力。 |
| 準2級 | より高度な学習を目指すために、あるいは、実社会での有効なコミュニケーションを実現するために必要な文章読解力及び文章作成力。 |
| 3級 | 高校での積極的な理解・表現活動、知的言語活動のために、あるいは、実社会におけるコミュニケーション活動を行うために必要な文章読解力及び文章作成力。 |
| 4級 | 読む・書く活動を円滑に行い、基礎的な知的言語活動を行うために必要な文章読解力及び文章作成力。 |
一応、3級が「高校」となっていますが、正直実体験からいえば平均的な国語力のある高校生なら、2級の合格もそれほど難易度が高くないと感じました。論文試験に自信がある高校生であれば、2級からの受験でもいいでしょう。
文章検定のメリットは?

取得することによる特別なメリットはありません。
もちろん、勉強を通して文章読解や文章を作成する能力は最低限身につくかなとは思います。ただ、大学生以上の場合は、実践の中で磨けば十分かなという印象もあり、試験を利用して学ぶということのメリットはあまり感じられませんでした。20代前半での就職・転職活動の場合、アピール方法にもよりますが「何も資格が無いよりは良い」という程度かなと思います。
一方、高校受験くらいであれば、2級でも十分評価されるのではないかと思います。中学生で、高校受験の勉強と論説文を書いた経験があれば、あとは手紙の書き方を覚えることで2級の合格も十分狙えます。受験タイミング的に利用できるのは中学2年生以下にはなりますが、少しでも受験を有利にしたいのであれば、狙ってみるのもいいかと思います。